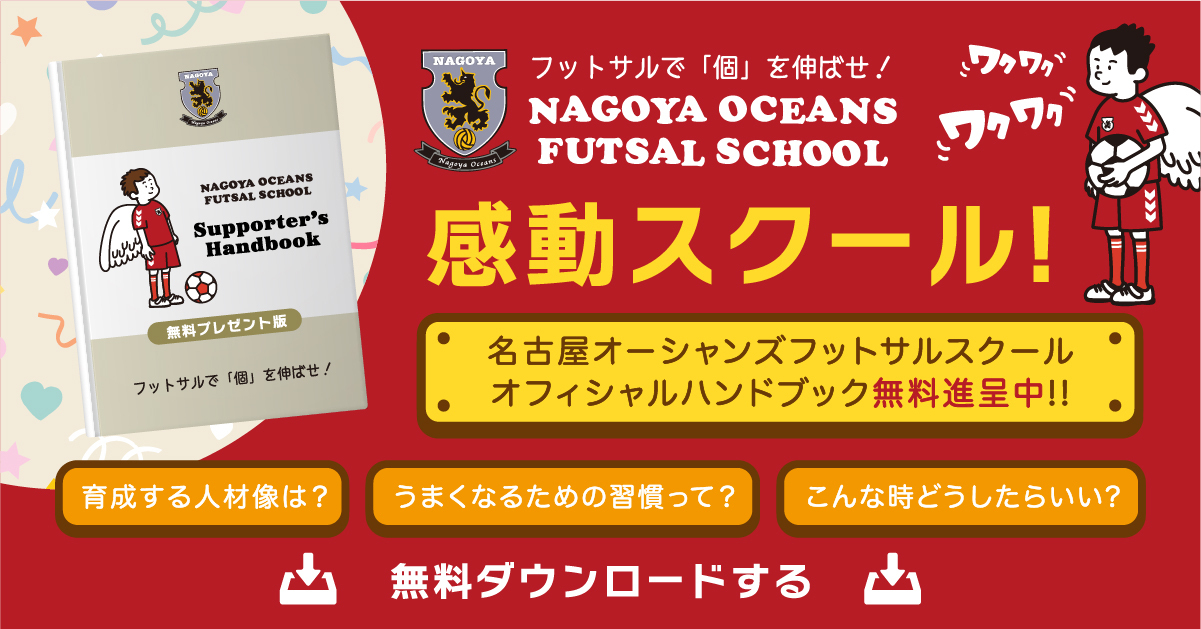2007年に日本で生まれた子どもは107歳まで生きる確率が50%という研究があるそうです。
また、幼児・小学生の子どもを持つ親世代が受けてきたつめこみ教育では解決できない物事が
増えてきています。
これからの子ども達は、正解がない世界、親も答えを教えられない時代に100年も
立ち向かわなければなりません。
では、これからの時代を生き抜くために必要な力とは具体的にどんな力でしょうか?
1. これからの時代に必要な力とは?
2. 社会人基礎力
3.スポーツが社会人基礎力を育む理由
4.サッカー・フットサルで身につく能力
5.バスケットボールで身につく能力
6.野球・ソフトボールで身につく能力
7.水泳で身につく能力
8.武道(柔道、剣道、空手など)で身につく能力
9.体操で身につく能力
これからの時代に必要な力とは?
例えば、困った時、乗り越えられないかもしれないという壁(問題・課題)に
突き当たった時、会社の買収合併・倒産など周囲の環境が著しく変化した時。
また、こうしたい、こうなりたいという欲求や夢・目標に向かって歩む時。
受け身で成り行きに任せるという、自分の人生を他人や周囲に委ねた生き方では
これからの時代を生き抜くことができません。自分で選択し、主体的に未来を
切り拓く、生き抜く力=問題解決力が必要です。
それは、壁を乗り越えた先のゴールを見定め、情報(学校で得た知識を含む)を
収集・分析し、考え、スピーディーにより最適な策を判断し、仲間や同僚などと協力し合いながら
行動する力です。これを問題解決力(課題達成力)と呼びます。
社会人基礎力
問題解決力につながる考え方として、経済産業省は「社会人基礎力」というものを提唱しています。経済産業省が提唱する「社会人基礎力」は、以下の3つの能力と12の能力要素から構成されています。

1. 前に踏み出す力(アクション)
・ 主体性:物事に進んで取り組む力
・ 働きかけ力:他人に働きかけ巻き込む力
・ 実行力:目的を設定し確実に行動する力
2. 考え抜く力(シンキング)
・ 課題発見力:現状を分析し目的や課題を明らかにする力
・ 計画力:課題の解決に向けたプロセスを明確にし準備する力
・ 想像力:新しい価値を生み出す力
3. チームで働く力(チームワーク)
・ 発信力:自分の意見をわかりやすく伝える力
・ 傾聴力:相手の意見を丁寧に聴く力
・ 柔軟性:意見の違いや立場の違いを理解する力
・ 情況把握力:自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力
・ 規律性:社会のルールや約束事を守る力
・ ストレスコントロール力:ストレスの発生源や対処法を理解する力
スポーツが社会人基礎力を育む理由
スポーツは、単に身体を動かすだけでなく、目標達成のために努力し、仲間と協力し、困難を乗り越える過程で様々な能力を育みます。
【 目標設定と達成】
試合での勝利、記録更新など、具体的な目標を設定し、それに向かって努力する過程で、計画力や実行力が養われます。
【チームワークとコミュニケーション】
団体競技では、仲間と協力し、声をかけ合い、役割を果たすことで、発信力、傾聴力、柔軟性、規律性が培われます。
【課題発見と解決】
練習や試合の中で、自分の課題やチームの課題を発見し、どのように改善していくかを考えることで、課題発見力や創造力が刺激されます。
【主体性と自律性】
練習メニューをこなしたり、体調管理をしたりする中で、主体性や自己管理能力が向上します。
【ストレス耐性とレジリエンス】
練習の辛さや試合でのプレッシャー、負けた時の悔しさなどを経験し、それらを乗り越えることで、ストレスコントロール力や逆境に立ち向かう力が養われます。
次の項目からは種目ごとに特に育まれる能力を考えていきます。
サッカー・フットサルで身につく能力
- チームで働く力: チームスポーツの代表格であり、仲間との連携が不可欠です。パス、ドリブル、シュートなど、それぞれの役割を理解し、お互いを信頼し、助け合うことで、発信力、傾聴力、柔軟性、規律性が飛躍的に向上します。
- 考え抜く力: 試合中に刻々と変化する状況を判断し、次にどう動くべきかを考えることで、状況把握力、課題発見力、計画力、創造力が養われます。例えば、相手のディフェンスをどう突破するか、どのタイミングでパスを出すかなど、常に状況判断が求められます。
- 前に踏み出す力: 積極的にボールに関わり、ゴールを目指す中で、主体性や実行力が育まれます。失敗を恐れずに挑戦する姿勢も身につきます。
ポイント
- 攻撃と守備の切り替えが早く、攻守において全員が関わるため、情況把握能力と臨機応機な対応力が求められます。
- 多様なポジションがあり、それぞれの役割を理解し、実行することで、責任感も養われます。

バスケットボールで身につく能力
- チームで働く力: コートが狭く、より密な連携が求められるため、仲間とのコミュニケーション能力が非常に重要になります。声かけはもちろん、アイコンタクトやジェスチャーなど、非言語コミュニケーション能力も向上します。
- 考え抜く力: 短時間で状況を判断し、パス、シュート、ドリブルの選択をする必要があります。相手の動きを読み、スペースを見つけることで、課題発見力、計画力、創造力が鍛えられます。
- 前に踏み出す力: オフェンスでもディフェンスでも、常に積極的に動くことが求められるため、主体性、実行力、働きかけ力が養われます。
ポイント
- 攻守の切り替えが非常に速く、瞬時の判断力と高い集中力が求められます。
- 限られた時間の中で得点を奪うという目標設定が明確で、目標達成へのプロセスを考える力が育まれます。

野球・ソフトボールで身につく能力
- チームで働く力: 攻撃と守備が明確に分かれ、それぞれで異なる役割を果たす必要があります。守備では連携プレー、攻撃ではバントや盗塁など、サインプレーを通じて仲間と協力する力が育まれます。
- 考え抜く力: 投球術や打撃フォームの改善、守備位置の判断など、戦略的な思考が求められます。試合展開を予測し、次の一手を考えることで、課題発見力、計画力、創造力が養われます。
- 前に踏み出す力: ヒットを打つ、盗塁を決める、アウトを取るなど、個人の努力がチームの勝利に直結するため、主体性と実行力が育まれます。失敗から学び、次に活かすレジリエンスも身につきます。
ポイント
- 個人プレーとチームプレーのバランスが良く、それぞれの重要性を学ぶことができます。
- 長い試合時間の中で、集中力を維持し、粘り強く取り組む力が養われます。

水泳で身につく能力
- 前に踏み出す力: タイムを縮める、泳法を習得するなど、明確な目標を設定し、それに向かって地道に努力する中で、主体性、実行力、自己管理能力が向上します。
- 考え抜く力: 効率的な泳ぎ方、呼吸法、ターンなど、フォームを改善するために試行錯誤することで、課題発見力、計画力、創造力が養われます。
- ストレスコントロール力: 長距離を泳ぐことによる肉体的な疲労や、タイムが伸び悩むなどの精神的なストレスを乗り越えることで、ストレス耐性が身につきます。
ポイント
- 個人競技ですが、記録会や大会を通じて目標を設定し、達成する喜びを味わうことができます。
- 全身運動であり、体力向上だけでなく、集中力や粘り強さも養われます。

武道(柔道、剣道、空手など)で身につく能力
- 規律性: 礼儀作法や道場の規律を守ることを徹底するため、社会のルールや約束事を守る力が自然と身につきます。
- 主体性・実行力: 技の習得や型稽古など、反復練習を通じて、地道な努力を続ける主体性と実行力が養われます。
- ストレスコントロール力: 稽古の厳しさや試合の緊張感の中で、自分を律し、精神力を鍛えることで、ストレスコントロール力や精神的な強さが育まれます。
- 傾聴力・発信力: 師範や先輩の指導を真剣に聞き入れ、自分の意見を明確に伝える中で、傾聴力と発信力が向上します。
ポイント
- 心身ともに鍛えられ、集中力、忍耐力、判断力といった精神的な強さが養われます。
- 相手を尊重し、感謝する気持ちを育むことで、人間関係を円滑にする力が身につきます。

体操で身につく能力
- 実行力: 複雑な技を習得するためには、地道な練習と反復が不可欠であり、目標に向かって着実に努力する実行力が養われます。
- 課題発見力・創造力: 自分の体の動きを分析し、どのようにすれば技を成功させられるかを考えることで、課題発見力や創造力が鍛えられます。
- ストレスコントロール力: 高い集中力を要する技の練習や、失敗への恐怖を乗り越えることで、ストレス耐性が向上します。
ポイント
- 柔軟性やバランス感覚だけでなく、集中力や忍耐力も高まります。
- 目標達成のために、諦めずに挑戦し続ける力が育まれます。

まとめ
どんなスポーツでもそれぞれの競技特性によって身につきやすい能力があることがわかります。
健康面や身体作りのためだけでなく、ぜひお子さんの好きなスポーツを経験させてみてください。