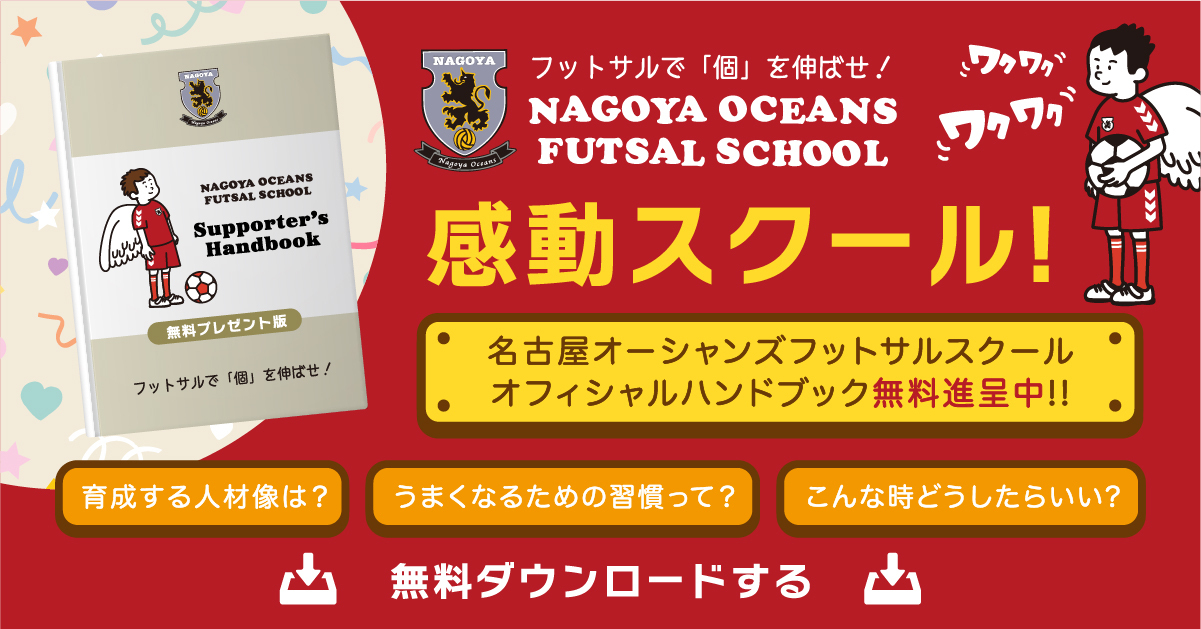こんにちは!
豊田校の鷲野です。
▶︎▶︎ “教えてもらってばかり”では大きく進めない
「なんでできなかったんだろう?」「じゃあ次はどうしてみよう?」
そんなふうに自分で考えてプレーできていますか?
スクールでは技術的なアドバイスはもちろんしますが、
僕が本当に大切にしたいのは「自分で考える力」。
その子の中にある「成長しようとする力」を信じて、
全部を教えすぎないことも、コーチの大切な仕事だと思っています。
今日はそんな「教えてもらってばかり」から一歩進んで、
自ら考える子どもたちの姿について書いてみます。
1. フットサルは“判断のスポーツ”
フットサルには、たくさんの「選択」があります。
パスか、ドリブルか、シュートか。どこに動くか、誰を見てプレーするか。
コートが狭く、敵も近く、展開も早い。
そんな中で一瞬で判断しなければならないからこそ、考える力が自然と鍛えられます。
だからこそ、プレーに「こうしなさい」と指示を出しすぎてしまうと、
子どもたちの判断する機会を奪ってしまうことになるんです。
2. 失敗が“考えるきっかけ”になる
「失敗は悪いこと」
そんなイメージを持ってしまう子もいます。
でも本当は逆で、失敗こそが“最高の学びのチャンス”だと思っています。
うまくいかなかったからこそ、「じゃあ次はどうする?」と考えられると思います。
コーチが全部答えを教えてしまうと、この「自分で考える時間」がなくなってしまう。
だからこそ、失敗に寄り添いつつも、
子どもたちが自分で答えを探せるように「聞く」ようにしています。
3. “待てる大人”でありたい
子どもたちが自分で気づくには、少し時間がかかることもあります。
そんな時は「待つ力」、「導く力」が必要になります。
つい口を出したくなる気持ちもあって、もっと上達してほしいという気持ちもあります。
でも、子どもたちの中から湧き上がってくる気づきやひらめきは、
何よりも価値のあるものだと思うんです。
「自分でつかんだ正解」は、一生ものの学びになると思います。
4. “自分の考えがある子”は強い
自分の頭で考え、選び、決めることができる子。
そんな子は、フットサルの中だけでなく、人生の中でも、
きっと力強く前に進んでいけるはずです。
「教えてもらう」から「自分でつかむ」へ。
そんな子どもたちの成長に、これからも寄り添っていきたいと思っています。